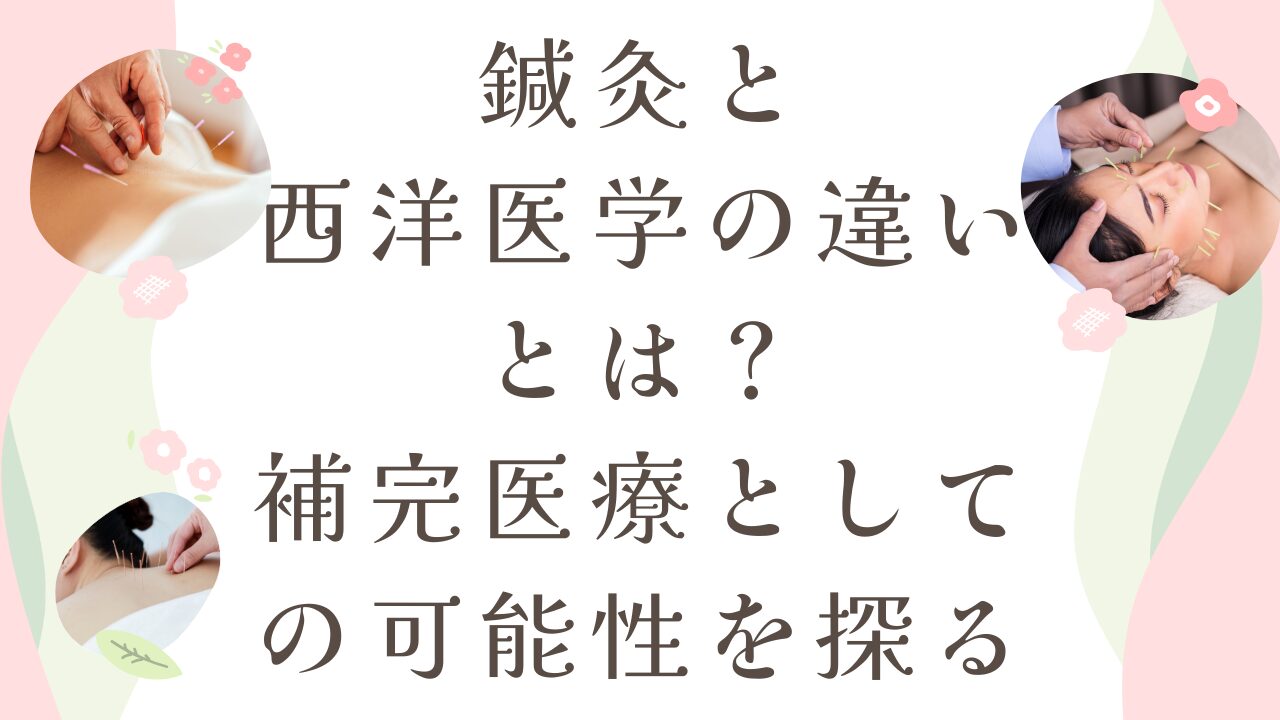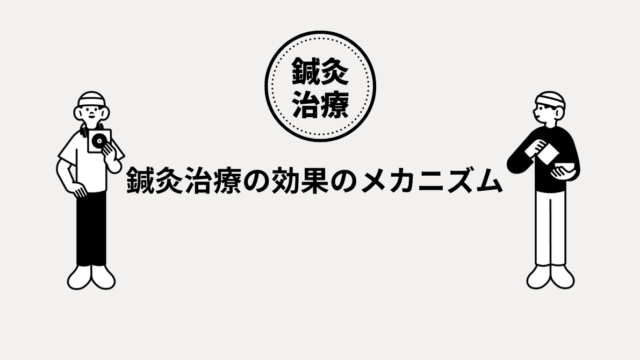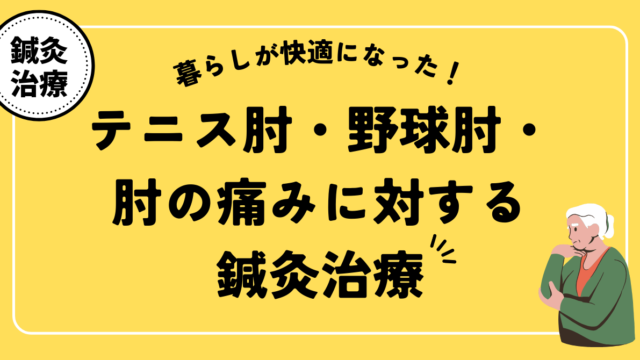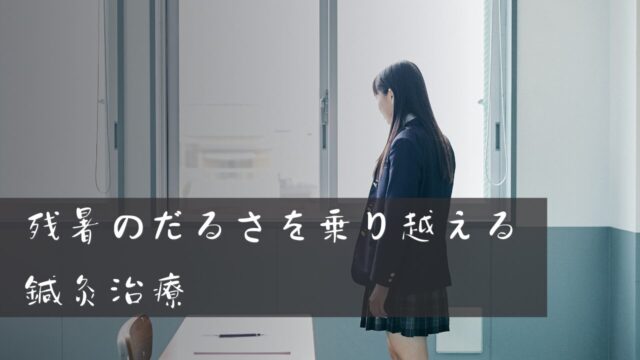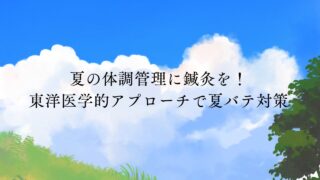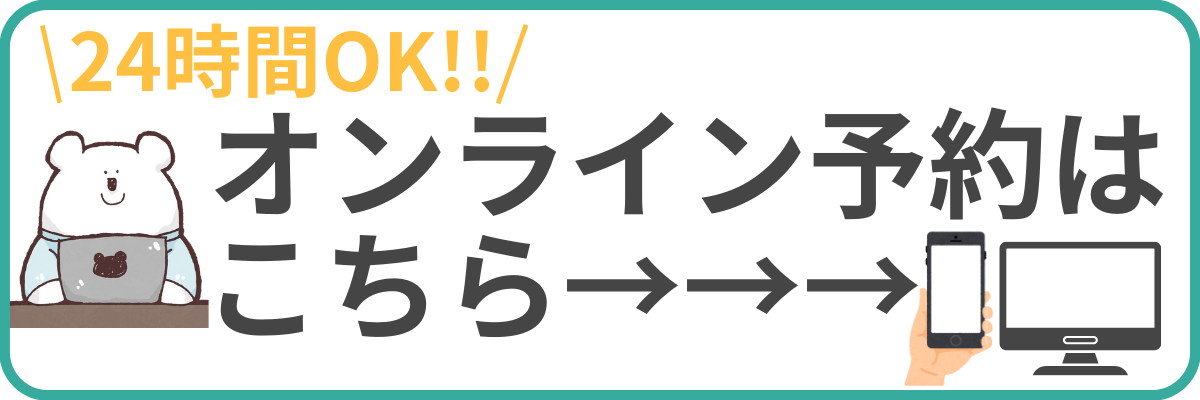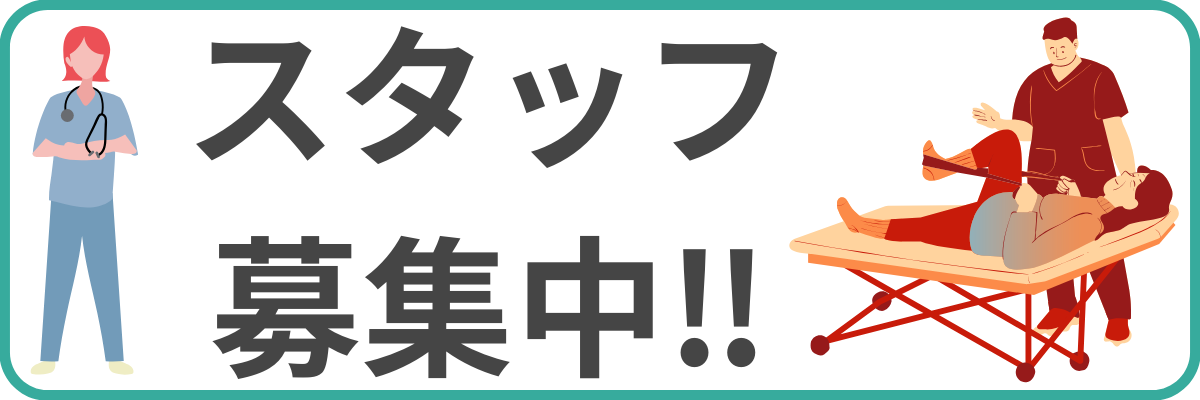「病院で検査を受けても異常はないけど、体がつらい…」
「薬に頼らず、体質から改善したい…」
そんなとき、注目されるのが東洋医学のひとつである鍼灸治療です。
この記事では、西洋医学と鍼灸の違い、そして補完医療としての可能性について解説します。
■ 鍼灸と西洋医学の大きな違い
簡単にまとめると、
- 西洋医学=対症療法(症状に直接アプローチ)
- 東洋医学(鍼灸)=原因療法(体全体のバランス調整)
西洋医学は、病気の原因を特定して、薬や手術などで直接治療します。
一方、鍼灸は「気・血・水」といった概念を用い、体の巡りを整えることで自然治癒力を高めるアプローチです。
■ なぜ「補完医療」として注目されているのか?
「補完医療(Complementary Medicine)」とは、西洋医学の治療に加え、
その効果を補うように組み合わせる医療のことです。
鍼灸は以下のような場面で、補完医療として活用されることが増えています。
✅ よくある適応例
- 自律神経の乱れや不眠
- 肩こり・腰痛などの慢性症状
- 生理痛・PMSなど婦人科系の悩み
- ストレス起因の不定愁訴
- 薬の副作用による不調
■ 医療は「どちらか」ではなく「組み合わせ」の時代
以前は、西洋医学か東洋医学かの“二択”で考えられることが多かったですが、
今は“併用する”という考え方が一般的になってきています。
たとえば、病院の治療を受けながら、鍼灸で自律神経を整えることで回復が早くなるケースもあります。
■ まとめ
鍼灸と西洋医学は、目的や方法こそ違いますが、どちらも「健康を守る」ための手段です。
「治らない」「薬が合わない」と感じたら、鍼灸という選択肢をぜひ思い出してみてください。
今のあなたに必要なのは、「治療」ではなく「整えること」かもしれません。